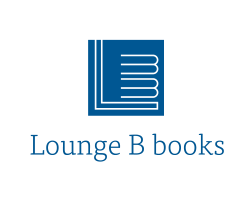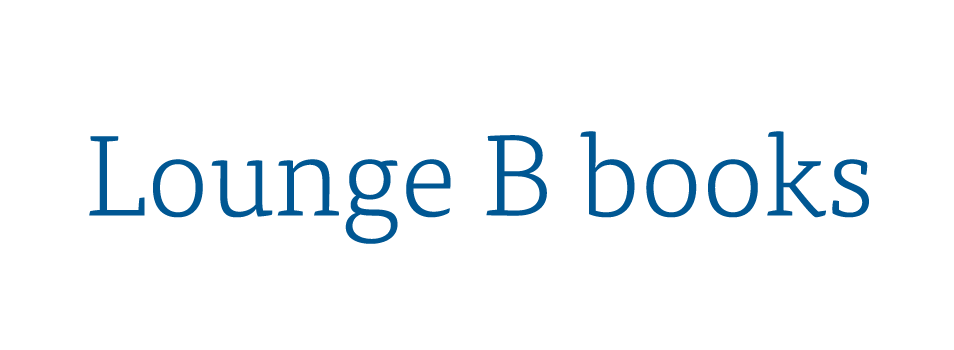-

『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす』朱 喜哲
¥2,420
SOLD OUT
正義は暴走しないし、人それぞれでもない──。 アメリカ大統領選挙から、日本の「道徳」の授業まで、現代において「正義」や「公正」といった「正しいことば」はどのように使われているかを検討。 ジョン・ロールズ、リチャード・ローティ、アイザイア・バーリン、ジュディス・シュクラー、アイリス・マリオン・ヤング、スタンリー・カヴェルなどの議論を参照しながら、「正しいことば」の使いこなし方をプラグマティズム言語哲学から探る。 「正しさ」とはなにかを考えるうえで、わたしたち自身の〝ことばづかい〞を通して「正しいことば」をとらえなおす画期的論考。
-

『生きる言葉』俵万智
¥1,034
SOLD OUT
スマホとネットが日常の一部となり、顔の見えない人ともコミュニケーションできる現代社会は、便利な反面、やっかいでもある。 言葉の力が生きる力とも言える時代に、日本語の足腰をどう鍛えるか、大切なことは何か──恋愛、子育て、ドラマ、歌会、SNS、AIなど、様々なシーンでの言葉のつかい方を、歌人ならではの視点で、実体験をふまえて考察する。 出版社:新潮社 発売日:2025.4 判型・製本:新書 ページ数:240

-

『日本語界隈』川添愛、ふかわりょう
¥1,760
SOLD OUT
ちょっとした日本語の言い回しでモヤモヤしているふかわさんと気鋭の言語学者・川添愛さんが、「言語学」という枠を超えて、日本語のユニークさと奥深さを楽しむ、異色の対談集。 ●トマトトマトしている!? ●「冬将軍」はあっても、「夏将軍」はない? ●「普通においしい」の「普通」って? ●「昼下がり」でなく、「昼上がり」なら情事はない? ●日本人が「ドラクエ」と略してしまうワケ ●「サボる」「ヤバい」の由来は? ●「汚い」と「小汚い」、どちらが汚い? 身近なのに意外とややこしい!? 繊細かつ頑固な「日本語」の素顔に迫る! 出版社:ポプラ社 発売日:024.10 判型・製本:四六判 ページ数:238

-

『言語学バーリ・トゥード Round 2 言語版SASUKEに挑む』川添愛
¥1,870
SOLD OUT
ことばの「なぜ?」に向き合う、爆笑必至エッセイ。 迷わず読めよ、読めばわかるさ レイザーラモンRGの「あるあるネタ」はどうしておもしろいのか。 「飾りじゃないのよ涙は」という倒置はなぜ印象的なのか。 猪木の名言から「接頭辞BLUES」まで縦横無尽に飛び回りながら、日常にある言語学のトピックを拾い出す。 【目次】 この本を手に取ってくださった皆様へ 1.生産者の顔が見える原稿 2.言語版SASUKEに挑む 3.言葉に引導を渡す者 4.あるあるネタはなぜ人を笑顔にしがち♪なのか 5.最高にイカすぜ、倒置は! 6.悪い言葉の誘惑 7.【コント】ミスリーディング・セミナー 8.2023年も“行けばわかるさ” 9.【創作】言語モデルに人生を狂わされた男 10.話題のAIをちょっと真面目に解説してみる 11.【創作】メトニミーのない世界 12.日本語は「世にも曖昧な言語」なのか 13.重言パラダイス 14.日本語は本当に「非論理的な言語」なのか 15.【コント】接頭辞BLUES あとがき 関連記事 出版社:東京大学出版会 発売日:2024.8 判型・製本:四六判 ページ数:240
-

『言語学バーリ・トゥード Round 1 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか』川添愛
¥1,870
読むなよ、絶対に読むなよ! ラッシャー木村の「こんばんは」に、なぜファンはズッコケたのか。ユーミンの名曲を、なぜ「恋人はサンタクロース」と勘違いしてしまうのか。 日常にある言語学の話題を、ユーモアあふれる巧みな文章で綴る。 【目次】 この本を手に取ってくださった皆様へ 1 「こんばんは事件」の謎に迫る 2 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか 3 注文(ちゅうぶん)が多めの謝罪文 4 恋人{は/が}サンタクロース? 5 違う,そうじゃない 6 宇宙人の言葉 7 一般化しすぎる私たち 8 たったひとつの冴えたAnswer 9 本当は怖い「前提」の話 10 チェコ語,始めました 11 あたらしい娯楽を考える 12 ニセ英語の世界 13 ドラゴンという名の現象(フェノメノン) 14 ことば地獄めぐり 15 記憶に残る理由 16 草が生えた瞬間 あとがき 出版社:東京大学出版会 発売日:2021.7 判型・製本:四六判 ページ数:224
-

『世にもあいまいなことばの秘密』川添愛
¥990
SOLD OUT
【版元HPより】 「この先生きのこるには」「大丈夫です」これら表現は、読み方次第で意味が違ってこないか。このような曖昧な言葉の特徴を知れば、余計な誤解もなくなるはず 「結構です」→YESNOどっち? 「それですね」→どれやねん 「この先生きのこるには」→先生! こうして誤解は広がっていく 「冷房上げてください」「大丈夫です」。 言葉には、読み方次第で意味が変わるものが多々あり、そのせいですれ違ったり、争ったりすることがある。 曖昧さの特徴を知り、言葉の不思議に迫ろう。 出版社:筑摩書房 発売日:2023.12 判型・製本:新書判 ページ数:240
-

『ヒトの言葉 機械の言葉 「人工知能と話す」以前の言語学』川添愛
¥990
私たちは本当に、「意味」が分かっているのか AIが発達しつつあるいま、改めて「言葉とは何か」を問い直す―― AIと普通に話せる日はくるか。 人工知能と向き合う前に心がけるべきことは。 そもそも私たちは「言葉の意味とは何か」を理解しているか。 出版社:KADOKAWA 発売日:2020.11 判型・製本:新書判 ページ数:256
-

『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 人工知能から考える「人と言葉」』川添愛(著)、 花松あゆみ(絵)
¥1,870
SOLD OUT
【版元HPより】 なぜAIは、囲碁に勝てるのに、簡単な文がわからないの? そもそも、言葉がわかるって、どういうこと? 中高生から大人まで「言葉を扱う機械」のしくみと、私たちの「わかり方」を考える。 なんでも言うことを聞いてくれるロボットを作ることにしたイタチ村のイタチたち。彼らは、「言葉がわかる機械ができたらしい」といううわさを聞いては、フクロウ村やアリ村や、その他のあちこちの村へ、それがどのようなものかを見に行きます。ところが、どのロボットも「言葉の意味」を理解していないようなのです―― この本では、「言葉がわかる機械」をめぐるイタチたちの物語と、 実際の「言葉を扱う人工知能」のやさしい解説を通して、 そうした機械が「意味がわかっていると言えるのか」を考えていきます。 はたして、イタチたちは何でもできるロボットを完成させ、ひだりうちわで暮らせるようになるのでしょうか? ロボットだけでなく、時に私たち人間も、言葉の理解に失敗することがありますが、なぜ、「言葉を理解すること」は、簡単なように見えて、難しいのでしょうか? 出版社:朝日出版社 発売日:2017.6 判型・製本:A5判・並製 ページ数:272
-

『悪い言語哲学入門』和泉悠
¥924
【版元HPより】 「あんたバカ?」「だって女/男の子だもん」。 私たちが何気なく使う多くの言葉のどこに問題があるのか? その善悪の根拠を問い、言葉の公共性を取り戻す。 私たちは言葉を使うことができるため、言葉については誰もが一過言あるかと思われるが、しかしどれだけ美文を理解したり、かけたとしても言語を理論的に理解しているとはいえない。 たとえば、本書のテーマのひとつとなる「悪口」についても、他者を傷つける言葉、などと考えられているかもしれないが、問題はそんなに簡単なものではない。 それだけでは、言葉の真の性質を理解するものにならないからである。 たとえば、メンタルが強いAさんがいて、その人に対して否定的なことをいう人がいるとする。メンタルがつよいAさんはそんな言葉では、傷つくことはない。 だとすると、ここで使われた言葉は「悪口」といえないのだろうか? もちろん、それには違和感を覚えるだろう、そのため、「悪口」が人を傷つける言葉という定義では、その構造を理解できないのである。 そこで悪口や、その他さまざまな意味での悪い言葉の現象について、そのメカニズムを理解する準備として、言語哲学を中心とした学術的研究において用いられる概念や理論を紹介していく。 そして、悪い言語に立ち向かうために、悪い言語とはなんなのかを探求していくことになる。 出版社:筑摩書房 発売日:2022.2 判型・製本:新書 ページ数:256
-

『言葉のズレと共感幻想』細谷功、佐渡島庸平
¥2,200
「人は言葉を過信している」「スティーブ・ジョブズも歴史に残らない気がする」――「思考」テーマの著作を出し続ける著述家・細谷功と、メガヒットを飛ばし続ける漫画編集者・佐渡島庸平という異色の取り合わせ。 言葉、物語、お金、労働、ルール、いいねエコノミー(共感資本主義・格差)、VR(仮想現実)などを俎上にのせ、現代社会を覆う「共感幻想」を「具体と抽象」の往来問答によって深く掘り下げていく。 出版社:dZERO 発売日:2022.1 判型・製本:四六判並製 ページ数:288
-

『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』今井むつみ
¥1,870
SOLD OUT
間違っているのは、「言い方」ではなく「心の読み方」 ビジネスで 学校で 家庭で …… 「うまく伝わらない」という悩みの多くは、 「言い方を工夫しましょう」「言い換えてみましょう」 「わかってもらえるまで何度も繰り返し説明しましょう」では解決しません。 人は、自分の都合がいいように、いかようにも誤解する生き物です。 では、都合よく誤解されないためにどうするか? 自分の考えを“正しく伝える”方法は? 「伝えること」「わかり合うこと」を真面目に考え、実践したい人のための1冊。 出版社:日経BP 発売日:2024.5 判型・製本:四六判 ページ数:304
-

『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』 今井むつみ、秋田喜美
¥1,056
SOLD OUT
日常生活の必需品であり、知性や芸術の源である言語。 なぜヒトはことばを持つのか? 子どもはいかにしてことばを覚えるのか? 巨大システムの言語の起源とは? ヒトとAIや動物の違いは? 言語の本質を問うことは、人間とは何かを考えることである。 鍵は、オノマトペと、アブダクション(仮説形成)推論という人間特有の学ぶ力だ。 認知科学者と言語学者が力を合わせ、言語の誕生と進化の謎を紐解き、ヒトの根源に迫る。 出版社:中央公論新社 発売日:2023.5 判型・製本:新書判 ページ数:296