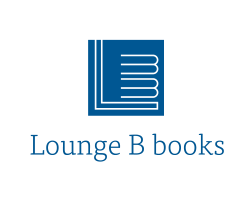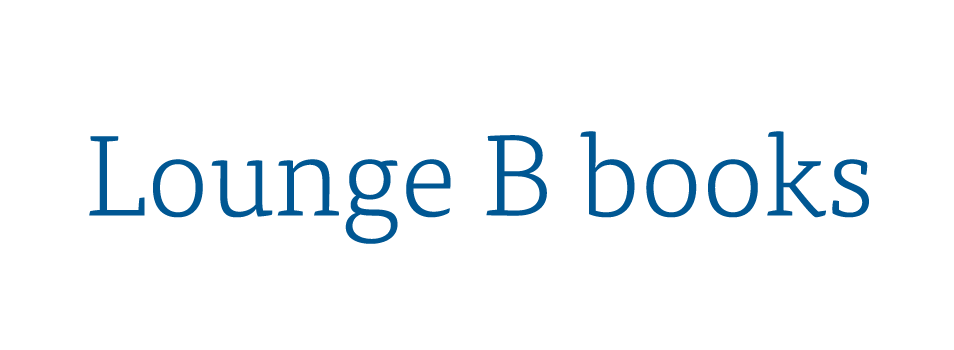-

『10:04』ベン・ラーナー(著)、木原善彦(訳)
¥3,190
ハリケーンの上陸が迫るニューヨーク、ブルックリン。 詩人である語り手の〝僕〟は前年に発表した小説デビュー作で思いもよらぬ評価を受けていた。 新たに『ニューヨーカー』誌に掲載された短編を組み込んで長編を書くと約束すれば、6桁強の原稿料が前払いでもらえるという。 その一方で、〝解離〟の可能性があると診断された〝僕〟の大動脈。 人工授精のために〝僕〟の精子を提供してほしいと言い出した親友の女性、アレックス。 ニューヨークの街を歩き回ったり、テキサス州マーファで芸術家としてレジデンス生活を送ったりしながら、〝僕〟は長編の構想を練る。 そして、自分がかつて雑誌を編集していたときに著名な詩人たちとの間で交わしたやり取りを偽造し、小説に取り込むことを思い付く……。
-

『夏のヴィラ』ペク・スリン(著)、カン・バンファ(訳)
¥1,870
SOLD OUT
初めてのヨーロッパ旅行で出会い親交を温めてきたドイツ人夫婦に誘われ、苦しい講師生活のなか気持ちがすれ違っていた夫と共に訪れたカンボジアのヴィラ。 数日過ごすうち、夫とドイツ人夫婦の間に小さな諍いが起こり……「夏のヴィラ」。 夫の希望で仕事を辞め、変わらない毎日を過ごすなかでの楽しみは、子供を送迎するときに見かける赤い屋根の家に住む空想をすることだった。 そんななか、親友が開業したイタリアンレストランで出会った若い男性とのささやかな会話が引き起こした心のさざ波に……「まだ家には帰らない」。 人と人、世界と世界の境界線を静かに描いた八つの短編を収録。
-

『まぶしい便り』ペク・スリン(著)、カン・バンファ(訳)
¥2,200
美しい文章とあたたかなまなざしで描くペク・スリンの初長編にして最高傑作 派遣看護師としてドイツに渡っていた伯母を頼り、母と幼い妹とともに西ドイツに移り住んだヘミ。 悲劇的な事故により心に傷を負ったまま、孤独な日々を過ごすヘミだったが、伯母と同じ派遣看護師のおばさんたちの子どもであるレナ、ハンスと過ごすうち、徐々に日常を取り戻していく。 ある日ハンスから、再発の可能性がある大病を抱える母親・ソンジャの初恋の相手を探してほしいと頼まれる。 ソンジャおばさんの日記を手がかりに捜索を始めたヘミだったが、急遽家族で帰国することに。 大人になったヘミは、ある日、大学時代にほのかな恋愛感情を抱いていたウジェと偶然再会する。 彼との会話をきっかけに、ヘミは再び、ソンジャおばさんの初恋の相手探しを再開する。
-

『ポップ・ラッキー・ポトラッチ』奥田亜希子
¥990
相田愛奈は、正しいことがなにより強いと信じている。 無職の彼女の銀行口座には、幸運に得た約2億円があるにもかかわらず、節制した生活を続けている。 その一方で、福祉団体等には多額の寄付をしていた。 そんな愛奈のもとに、無職かつ浪費家の従姉妹・忍が転がり込んできた。 さらに、Amazonの<ほしい物リスト>で約3万円分の品を贈った相手から、お礼らしいお礼がないことに愛奈は気づく。 なぜ? どうして? 数々の出来事が正しさセンサーに引っ掛かり、悶々とする愛奈の日々が始まった。
-

『ギリシャ語の時間』ハン・ガン(著)、斎藤真理子(訳)
¥1,980
ある日突然言葉を話せなくなった女は、失われた言葉を取り戻すために古典ギリシャ語を習い始める。 ギリシャ語講師の男は次第に視力を失っていく。 ふたりの出会いと対話を通じて、人間が失った本質とは何かを問いかけていく。 韓国の若い作家を紹介するシリーズ〈韓国文学のオクリモノ〉第1回配本。
-

『最初の哲学、最後の哲学』 ジョルジョ・アガンベン(著)、岡田温司(訳)
¥2,090
西洋の知を支配し諸科学を基礎づけてきた形而上学に、いまなお存在意義はあるのか。 アリストテレス、スコトゥス、カント、ハイデガーを読み解きながら哲学史における形而上学の機能を剔抉し、その放浪の歴史を描き出す。アガンベンによる最良の形而上学入門!
-

『ギンイロノウタ』村田沙耶香
¥693
少女の顔をした、化け物が目覚める。 戦慄の女子小説、誕生! 極端に臆病な幼い有里の初恋の相手は、文房具屋で買った銀のステッキだった。 アニメの魔法使いみたいに杖をひと振り、押入れの暗闇に銀の星がきらめき、無数の目玉が少女を秘密の快楽へ誘う。 クラスメイトにステッキが汚され、有里が憎しみの化け物と化すまでは……。 少女の孤独に巣くう怪物を描く表題作と、殺意と恋愛でつむぐ女子大生の物語「ひかりのあしおと」。 衝撃の2編。
-

『タダイマトビラ』村田沙耶香
¥572
帰りませんか、「家族」の無い純粋な世界へ。 新芥川賞作家が放つ衝撃の自分探し物語。 母性に倦んだ母親のもとで育った少女・恵奈は、「カゾクヨナニー」という密やかな行為で、抑えきれない「家族欲」を解消していた。 高校に入り、家を逃れて恋人と同棲を始めたが、お互いを家族欲の対象に貶め合う生活は恵奈にはおぞましい。 人が帰る所は本当に家族なのだろうか? 「おかえり」の懐かしい声のするドアを求め、人間の想像力の向こう側まで疾走する自分探しの物語。
-

『コンビニ人間』村田沙耶香
¥693
36歳未婚、彼氏なし。コンビニのバイト歴18年目の古倉恵子。 日々コンビニ食を食べ、夢の中でもレジを打ち、 「店員」でいるときのみ世界の歯車になれる――。 「いらっしゃいませー!!」 お客様がたてる音に負けじと、今日も声を張り上げる。 ある日、婚活目的の新入り男性・白羽がやってきて、 そんなコンビニ的生き方は恥ずかしい、と突きつけられるが……。
-

『信仰』村田沙耶香
¥715
SOLD OUT
「なあ、俺と、新しくカルト始めない?」 好きな言葉は「原価いくら?」 現実こそが正しいのだと強く信じる、超・現実主義者の私が、 同級生から、カルト商法を始めようと誘われて――。 世界中の読者を熱狂させる、村田沙耶香の11の短篇+エッセイ。 文庫化にあたり、短篇小説「無害ないきもの」「残雪」、エッセイ「いかり」を追加。 書き下ろしエッセイ「書かなかった日記――文庫版によせて」を巻末に収録。
-

『新版 映画の構造分析』内田樹
¥2,420
映画に隠された驚くべき物語構造を読み解く、 スクリーンから学べる現代思想、精神分析、ジェンダー。 大幅増補の決定版映画論。 物語には構造があり、映画にも構造がある。 そして映画の構造を知ることが、人間の欲望の構造を知ることにつながる……。 『エイリアン』『大脱走』『裏窓』などハリウッド映画の名作を題材にした映画論にして、ラカンやフーコーなど現代思想の入門テキストとして高い評価を受けた旧版『映画の構造分析』に、『君たちはどう生きるか』『ドライブ・マイ・カー』『怪物』『福田村事件』など、近年の話題作を分析した論考を大幅増補した決定版映画論。 〔2003年初版〕
-

『新版 就職しないで生きるには』レイモンド・マンゴー(著)、中山容(訳)
¥2,090
SOLD OUT
働き方・ライフスタイル本の原点 自分のリズムにあわせて働き、好きなことで生計を立てる。 40年以上にわたり若者たちを励ましてきた不朽の名著。 仕事と生き方に悩むすべての人に。 嘘にまみれて生きるのはイヤだ。 だが生きていくためにはお金がいる。 だから自分の生きるリズムにあわせて労働し、人びとが本当に必要とするものを売って暮らすのだ。 天然石鹸をつくる。 小さな本屋を開く。 その気になれば、シャケ缶だってつくれる。 頭とからだは自力で生きぬくために使うのだ。 失敗してもへこたれるな。 ゼロからはじめる知恵を満載した若者必携のテキスト。 〔1981年初版〕
-

『アルテミオ・クルスの死』フエンテス(作)、 木村榮一(訳)
¥1,320
大地主の私生児として生まれ、混血の伯父に育てられ、革命軍に参加し、政略結婚によって財産の基礎をつくり、政治を巧みに利用して、マスコミを含む多くの企業を所有する――。 メキシコ革命の動乱を生き抜いて経済界の大立者に成り上がった男アルテミオ・クルスの栄光と悲惨。 現代ラテンアメリカ文学の最重要作.
-

『詩人なんて呼ばれて』谷川俊太郎(語り手・詩) 、尾崎真理子(聞き手・文)
¥1,045
『二十億光年の孤独』刊行以降、常に日本語の可能性を拡げ続けてきた革新的詩人、谷川俊太郎。 その70年以上にわたる創作生活の全てを、多彩な作品を交えて振り返る。 哲学者・谷川徹三との父子関係、3人目の妻・佐野洋子との別れの真相、迫りくる老いと死への想い。 長時間の入念なインタビューによって浮かび上がる詩人の素顔とは。
-

『さよならは仮のことば―谷川俊太郎詩集―』谷川俊太郎
¥649
「僕はやっぱり歩いてゆくだろう……すべての新しいことを知るために/そして/すべての僕の質問に自ら答えるために」(「ネロ」)。 19歳でデビュー以来、70年にわたって言葉の可能性を追求し続けてきた国民的詩人。 国語教科書の定番「朝のリレー」「春に」、東日本大震災で話題となった「生きる」等、豊饒かつ多彩な作品群から代表作を含め独自に編集。 その軌跡をたどり、珠玉を味わう決定版詩集。
-

『夜のミッキー・マウス』谷川俊太郎
¥407
SOLD OUT
詩人はいつも宇宙に恋をしている。 作者にも予想がつかないしかたで生れてきた言葉が、光を放つ。 「夜のミッキー・マウス」「朝のドナルド・ダック」「詩に吠えかかるプルートー」そして「百三歳になったアトム」。 ミッキー・マウスもドナルド・ダックもプルートーもアトムも、時空を超えて存在している。 文庫版のための書下ろしの詩「闇の豊かさ」も収録。 現代を代表する詩人の彩り豊かな30篇。
-

『ベージュ』谷川俊太郎
¥506
SOLD OUT
虚空に詩を捧げる/形ないものにひそむ/原初よりの力を信じて(「詩の捧げ物」)。 弱冠18歳でのデビューから70余年。 谷川俊太郎の詩は、私たちの傍らで歌い、囁き、描き、そしてただ在り続けた。 第一詩集『二十億光年の孤独』以来、第一線で活躍する谷川がくりかえし言葉にしてきた、誕生と死。 若さと老い。 忘却の快感。 そして、この世界の手触り。 長い道のりを経て結実した、珠玉の31篇を収録。
-

『62のソネット+36』谷川俊太郎
¥880
未発表36篇を含む青春の詩を、二ヵ国語版で現代詩の巨人・谷川俊太郎の第二詩集を、日英の二ヵ国語版で文庫化。 22歳の著者が詠んだ、祈りにも似た愛と生へのほめうた。 半世紀を超えて読み継がれる青春の書の決定版!
-

『ディア・ライフ』アリス・マンロー(著) 、小竹由美子(訳)
¥2,530
チェーホフ以来もっとも優れた短篇小説家が、透徹した眼差しとまばゆいほどの名人技で描きだす、平凡な人びとの途方もない人生、その深淵。 引退を表明しているマンロー自身が〈フィナーレ〉と銘打ち、実人生を語る作品と位置づける「目」「夜」「声」「ディア・ライフ」の四篇を含む全十四篇。
-

『ピアノ・レッスン』アリス・マンロー(著) 、小竹由美子(訳)
¥2,750
行商に同行した娘は父のもう一つの顔を目撃し、駆出しの小説家は仕事場で大家の不可思議な言動に遭遇する。 心を病んだ母を看取った姉は粛然と覚悟を語り、零落したピアノ教師の老女が開く発表会では小さな奇跡が起こる――人生の陰翳を描き「短篇の女王」と称されるカナダ人ノーベル賞作家の原風景に満ちた初期作品集。
-

『善き女の愛』アリス・マンロー(著) 、小竹由美子(訳)
¥2,640
独身の善良な訪問看護婦が元同級生に寄せる淡い思いと、死にゆくその妻。 三者の心理的駆け引きをスリリングに描くO・ヘンリー賞受賞の表題作ほか、母と娘、夫と妻、嫁と小姑など、誰にも覚えのある家族間の出来事を見事なドラマとして描きだす、マンローの筆が冴える金字塔的短篇集。
-

『二木先生』 夏木志朋
¥858
文庫。 どうしたら普通に見えるんだろう。 どうしたら普通に話せるんだろう――。 いつもまわりから「変」と言われ続けてきた高校生の田井中は、自分を異星人のように感じていた。 友だちが欲しいなんて贅沢なことは言わない。 クラスのなかで普通に息さえできたなら。 そのためならば、とむかしから好きでもない流行りの歌を覚え、「子供らしくない」と言われれば見よう見まねで「子供らしく」振舞ってもみた。 でも、ダメだった。 何をやっても浮き上がり、笑われてしまう。 そんな田井中にとって唯一の希望は、担任の美術教師・二木の存在だった。 生徒から好かれる人気教師の二木だったが、田井中はこの教師の重大な秘密を知っていたのだ。 生きづらさに苦しむ田井中は二木に近づき、崖っぷちの「取引」を持ち掛ける――。 社会から白眼視される「性質」をもった人間は、どう生きればよいのか。 その倫理とは何か。 現代の抜き差しならぬテーマと向き合いつつ予想外の結末へと突き抜けていく、驚愕のエンタテインメント。
-

『鷲か太陽か?』オクタビオ・パス(著)、 野谷文昭(訳)
¥792
ノーベル賞詩人オクタビオ・パス(1914-98)がパリに暮らした一九四〇年代後半に創作した散文詩と、イメージとリズムの法則に支配された、夢のような味わいをもつ短篇。 シュルレアリスムの正統的・批判的継承者として知られる巨匠による、研ぎ澄まされた詩的直観が鮮烈な印象を残す初期の代表作。
-

『ケアしケアされ、生きていく』竹端寛
¥946
ケアは「弱者のための特別な営み」ではない。あなたが今生きているのは赤ん坊の時から膨大な「お世話」=ケアを受けたから。身の回りのそこかしこにケアがある。 他人に迷惑をかけていい!! ケアは弱者のための特別な営みではない。社会の抑圧や呪縛から抜けだして、自分のありのままを大切にするような、お互いがケアしケアされるそんな社会を目指そう! 出版社:筑摩書房 発売日:2023.10 判型・製本:新書 ページ数:208