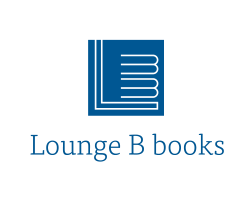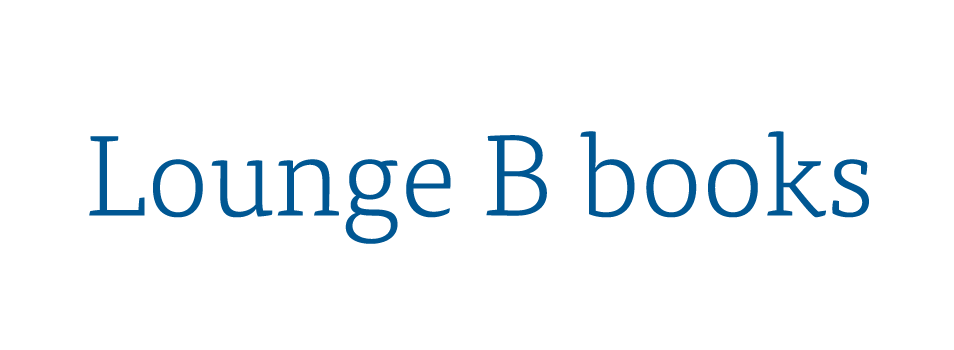-

『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす』朱 喜哲
¥2,420
SOLD OUT
正義は暴走しないし、人それぞれでもない──。 アメリカ大統領選挙から、日本の「道徳」の授業まで、現代において「正義」や「公正」といった「正しいことば」はどのように使われているかを検討。 ジョン・ロールズ、リチャード・ローティ、アイザイア・バーリン、ジュディス・シュクラー、アイリス・マリオン・ヤング、スタンリー・カヴェルなどの議論を参照しながら、「正しいことば」の使いこなし方をプラグマティズム言語哲学から探る。 「正しさ」とはなにかを考えるうえで、わたしたち自身の〝ことばづかい〞を通して「正しいことば」をとらえなおす画期的論考。
-

『最初の哲学、最後の哲学』 ジョルジョ・アガンベン(著)、岡田温司(訳)
¥2,090
西洋の知を支配し諸科学を基礎づけてきた形而上学に、いまなお存在意義はあるのか。 アリストテレス、スコトゥス、カント、ハイデガーを読み解きながら哲学史における形而上学の機能を剔抉し、その放浪の歴史を描き出す。アガンベンによる最良の形而上学入門!
-

『「透明」になんかされるものか 鷲田清一エッセイ集』鷲田清一
¥2,035
SOLD OUT
朝日新聞『折々のことば』でおなじみの哲学者・鷲田清一、6年ぶりのエッセイ集! 2019年以降、ウクライナや震災、コロナなど、未曾有の日々に起こった社会のできごとに隠れた本質的な問いを、深くやさしい言葉で解き明かす。 疑いもなくじぶんはここにいる(はず)なのに、それがだれにも見えていない、このことを「透明」というふうに表現している文章に、ここ数日間のあいだに立て続けに出会った。[…] この社会で「マイナー」とみなされてきた人びとの存在。生き物としての市民一人ひとりの生活を維持するのに不可欠な装置とそれに従事する人びとの労働。それらはまるでシャッターを下ろすかのように、「マジョリティ」の視線から外されてきた。[…]見えているのにだれも見ていないものを見えるようにするだけでなく、だれかの存在をそのように見えなくしている社会の構造そのものを見えるようにしていかなければならない。社会について考えるということには、少なくともそうした課題が含まれているとおもう。――プロローグより ・コロナの経験をどのように人類は今後に生かしていくのか ・ウクライナやガザなど彼の地で起こっている戦争をどう受け止め、日本にいる私たちにできることは一体何なのか ・旧ジャニーズや政治家の、会見での一連の不均衡さはなぜ起こるのか ・「SDGs」という正しい言葉への不信感 …… 日々目にするニュースをどう受け止めればよいかわからない人、さらに一歩踏み込んで考えてみたい方に。 出版社:朝日新聞出版 発売日:2025.5 判型・製本:四六判 ページ数:284

-

『「聴く」ことの力』 鷲田清一
¥1,100
「聴く」―目の前にいる相手をそのまま受け止めるいとなみが、他者と自分理解の場を劈く。本書は、不条理に苦しむこころからことばがこぼれ落ちるのを待ち、黙って迎え入れる受け身の行為がもたらす哲学的可能性を模索する。 さらにメルロ=ポンティ、ディディエ・アンジュー、レヴィナスなどを援用しつつ、ケアの現場や苦しみの現場において思考を重ねることで、「臨床哲学」という新しい地平を生み出した。 出版社:筑摩書房 発売日:2015.4 判型・製本:文庫 ページ数:288
-

『想像のレッスン』鷲田清一
¥1,034
SOLD OUT
「他者の未知の感受性にふれておろおろするじぶんをそのまま晒けだしたかった」という著者のアート評論。 かすかな違和の感覚を掬い取るために日常の「裂け目」に分け入り、「見る」ことの野性を甦らせるアートの跳躍力とは。アート、演劇、舞踏、映画、写真、音楽、ファッションなどについて、「ここにあるものを手がかりにここにないものを思う」評論集。 出版社:筑摩書房 発売日:2019.5 判型・製本:文庫 ページ数:336
-

『〈新生〉の風景 ロラン・バルト、コレージュ・ド・フランス講義』原宏之(著)、管啓次郎(解説)
¥2,530
SOLD OUT
ロラン・バルト生誕から110年。 バルトが最晩年にコレージュ・ド・フランスでおこなった「「新生」講義」の全容を紹介した、2002年刊行の同名書を新装刊。 自身の老い、母の死、新生、小説……。 バルト自身の声に寄りそいながら、従来のバルト像と「書くこと」をめぐる問いに変容をもたらした、小粒ながら意義ある仕事に、詩人/文学批評家の管啓次郎が解説を添える。 出版社:書肆水月 発売日:2025.4 判型・製本:四六判・並製 ページ数:216

-

『星になっても』岩内章太郎
¥1,980
SOLD OUT
最期に交わした会話、柩に供えたアップルパイ、死後に読んだ父の手記……そうやって、父の死について書いていくうちに起きた心境の変化は、私の、あるいは、私の哲学の核心に触れるものだった。 哲学者の著者が、父の死をきっかけに書き綴った、喪失と回復の道のりを優しくたどるエッセイ。 「どうしてじいじは死んじゃったの?」 息子の問いに、私はうまく答えることができなかった。 大切な人を亡くしたとき、私たちはどうやってそれを受け止めたらいいんだろう? 出版社:講談社 発売日:2025.4 判型・製本:四六判 ページ数:256

-

『アンチ・アンチエイジングの思想 ボーヴォワール『老い』を読む』上野千鶴子
¥2,970
老いには誰も抗えない。 それなのに、私たちはなぜ老いを恐れるのだろう。 平均寿命が延び、老人としての生が長くなったことで、誰もが老いに直面すると同時に不安も高まっている。 自分が老いたことを認めたくないのは、社会が老いを認めないからだ。 それを惨めにしているのは文明のほうなのだ。 「老いは文明のスキャンダルである」――この言葉に導かれて、ボーヴォワール『老い』への探究がはじまる。 さらに日本の介護の現場を考察し、ボーヴォワールのみた景色の先へと進む。 認知症への恐怖、ピンピンコロリという理想、安楽死という死の権利。 その裏側にある老いへの否定から見えてくるのは、弱いまま尊厳をもって生ききるための思想がぜひとも必要だということだ。 ひとが最後の最後まで人間らしく生きるには、徹底的な社会の変革が必要なのだ。 老いて弱くなることを否定する「アンチエイジング」にアンチをとなえ、老い衰え、自立を失った人間が生きる社会を構想する。 出版社:みすず書房 発売日:2025.4 判型・製本:四六判 ページ数:328

-

『100分de名著 ボーヴォワール『老い』 2021年7月』
¥660
老いは不意にあなたを捉える 見たくない、聞きたくない、考えたくない――。 そんな「老い」の実態をあらゆる観点から論じ、従来のステレオタイプを次々と打ち砕いたボーヴォワールの主著。 なぜ老いを自覚することは難しいのか。 老人が社会から疎外される根本理由とは。 キレイゴト抜きに「老い」の実態を暴き、「文明のスキャンダル」と捉え直した著作の真価を、現代日本の状況にも引きつけながらやさしく解説する。 出版社:NHK出版 発売日:2021.6 判型・製本:A5判 ページ数:116
-

『第二の性 Ⅱ 体験(下)』シモーヌ・ド・ボーヴォワール
¥1,320
上巻に続き、現代の女たちの生を分析する。 母親、社交生活、売春婦と高級娼婦、熟年期から老年期へ、ナルシシストの女、恋する女、神秘的信仰に生きる女から、自立した女、そして解放まで。 出版社:河出書房新社 発売日:2023.4 判型・製本:文庫 ページ数:520
-

『第二の性 Ⅱ 体験(上)』シモーヌ・ド・ボーヴォワール
¥1,320
Ⅰ巻の「事実と神話」をもとに、現代の女たちの生を、さまざまな文学作品や神話、精神分析を渉猟しつつ分析する。 子ども時代、娘時代から、性の入門、同性愛の女、結婚した女まで。 出版社:河出書房新社 発売日:2023.4 判型・製本:文庫 ページ数:488
-

『第二の性 Ⅰ 事実と神話』シモーヌ・ド・ボーヴォワール
¥1,485
「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」。 神話、文学、生理学、精神分析など、男に支配されてきた女の歴史を紐解きながら、女たちの自由な可能性を提示する20世紀の画期的名著。 出版社:河出書房新社 発売日:2023.3 判型・製本:文庫 ページ数:568
-

『非美学 ジル・ドゥルーズの言葉と物』福尾匠
¥2,970
非美学は、批評の条件についての哲学的思考である。 非美学は他者から〈眼を逸らす〉ことの意味を思考する試みである。 哲学を「概念の創造」として定義したドゥルーズにとって、芸術を通して概念を創造する批評とは何だったのか―― ドゥルーズに伏在する「言葉と物」の二元論から、今世紀の日本の批評を導いてきた「否定神学批判」の限界に迫る、 俊英による真の現代思想がここに! 他者から〈眼を逸らす〉ことの意味は、いかにして思考可能なのか? われわれの現代思想はここから始まる! 出版社:河出書房新社 発売日:2024.6 判型・製本:四六判 ページ数:466
-

『ひとごと クリティカル・エッセイズ』福尾匠
¥2,750
すべて「じぶんごと」として考えることを迫られる時代に「ひとごと」そのものを思考する倫理を立ち上げる。 気鋭の思想家がデビュー以来綴ってきた批評=エッセイが哲学へと結実する実践の書 【目次】 スモーキング・エリア#1 煙草と同じくらい分煙が好き 100パーセントの無知の男の子と出会う可能性について 非美学=義家族という間違った仮説をもとに ポシブル、パサブル――ある空間とその言葉 スモーキング・エリア#2 音響空間の骨相学 コントラ・コンテナ──大和田俊《Unearth》について プリペアド・ボディ――坂本光太×和田ながら「ごろつく息」について スパムとミームの対話篇 スモーキング・エリア#3 僕でなくもない やさしさはひとにだれかのふりをさせる――大前粟生『私と鰐と妹の部屋』について感じたらこの法螺貝を吹いてください――『全裸監督』について 異本の論理――アラン・ロブ=グリエ『ヨーロッパ横断特急』について 絵画の非意識――五月女哲平の絵画について 失恋工学概論 スモーキング・エリア#4 時間の居残り 見て、書くことの読点について テーブルクロス・ピクチャープレーン――リー・キット「僕らはもっと繊細だった。」展について 日記を書くことについて考えたときに読んだ本――滝口悠生『長い一日』について ひとんちに日記を送る Tele-visionは離れて見てね 画鋲を抜いて剝がれたらそれは写真――迫鉄平「FLIM」展について ジャンルは何のために?――絵画の場合(千葉正也、ロザリンド・クラウス、本山ゆかり) スモーキング・エリア#5 痛み、離人、建て付けの悪い日々 長続きしないことについて 「新実在論」はどう響くのか――『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する』について 思弁的実在論における読むことのアレルギー 廣瀬純氏による拙著『眼がスクリーンになるとき』書評について 映像を歩かせる――佐々木友輔『土瀝青asphalt』および「揺動メディア論」論 〈たんに見る〉ことがなぜ難しいのか――『眼がスクリーンになるとき』について 初出一覧・解題 出版社:河出書房新社 発売日:2024.11 判型・製本:四六判 ページ数:280
-

『哲学の教科書 ドゥルーズ初期』ジル・ドゥルーズ
¥1,210
高校教師だったドゥルーズが教科書として編んだ、全66編の哲学アンソロジー『本能と制度』ほか、幻の名著を詳細な訳注によって解説し、ドゥルーズの思考の原点を明らかにする。 新装版。 出版社:河出書房新社 発売日:2025.2 判型・製本:文庫 ページ数:256
-

『中動態の世界─意志と責任の考古学─』國分功一郎
¥990
誰かを好きになる。 これは能動か受動か。 好きになろうとしたのでもなければ、好きになるよう強いられたのでもない。 自分で「する」と人に「される」しか認めない言葉は、こんなありふれた日常事を説明することすらできない。 その外部を探求すべく、著者は歴史からひっそりと姿を消した“中動態”に注目する。 人間の不自由さを見つめ、本当の自由を求める哲学書。時代を画する責任論を新たに収録。 出版社:新潮社 発売日:2025.3 判型・製本:文庫 ページ数:528

-

『その悩み、カントだったら、こう言うね。』秋元康隆
¥1,980
人間は倫理なしには生きられない 正直者はバカを見る? 結果がすべては本当か? 悪とはなにか? ──リアルな問いを自分の頭で考えてみよう。 日常の悩みに答える前半部と、学問上の疑問に答える後半部の二部構成でおくる、Q&A式・カント倫理学への招待状。 出版社:平凡社 発売日:2025.4 判型・製本:四六判並製 ページ数:224

-

『荘子の哲学』山田史生
¥2,750
考えるな、 見よ! 感じろ! 西洋哲学に伍すべき東洋の叡智はなにかといえば、それは荘子の万物斉同の哲学だ。この世界はどういうものであり、 そこで人間が生きるとはどういうことか、を論じたものだ。 SNSに雁字がらめになっている現代社会だからこそ、荘子の哲学のエッセンスであり深奥である斉物論篇を読み解く。 出版社:トランスビュー 発売日:2025.3 判型・製本:四六判 ページ数:232

-

『訂正可能性の哲学』東浩紀
¥2,860
「本書は、五十二歳のぼくから二十七歳のぼくに宛てた長い手紙でもある──」 世界を覆う分断と人工知能の幻想を乗り越えるためには、「訂正可能性」に開かれることが必要だ。ウィトゲンシュタインを、ルソーを、ドストエフスキーを、アーレントを新たに読み替え、ビッグデータからこぼれ落ちる「私」の固有性をすくい出す。 『観光客の哲学』をさらに先に進める、『存在論的、郵便的』から四半世紀後の到達点。 出版社:ゲンロン 発売日:2023.9 判型・製本:四六判 ページ数:364
-

『観光客の哲学 増補版』東浩紀
¥2,640
第71回毎日出版文化賞、紀伊國屋じんぶん大賞2018でも第2位にランクインした『ゲンロン0 観光客の哲学』が新章2章・2万字を追加した増補版として刊行。 出版社:ゲンロン 発売日:2023.6 判型・製本:四六判 ページ数:424
-

『生きる言葉』俵万智
¥1,034
SOLD OUT
スマホとネットが日常の一部となり、顔の見えない人ともコミュニケーションできる現代社会は、便利な反面、やっかいでもある。 言葉の力が生きる力とも言える時代に、日本語の足腰をどう鍛えるか、大切なことは何か──恋愛、子育て、ドラマ、歌会、SNS、AIなど、様々なシーンでの言葉のつかい方を、歌人ならではの視点で、実体験をふまえて考察する。 出版社:新潮社 発売日:2025.4 判型・製本:新書 ページ数:240

-

『歩くという哲学』フレデリック・グロ(著)、谷口亜沙子(訳)
¥2,640
SOLD OUT
【版元HPより】 世界中に影響を与え、世界を動かした思想家、哲学者、作家、詩人の思索の多くは、歩くことによって生まれてきました。 歩くことは、最もクリエイテブな行為なのです。 また素晴らしいアイデアを出す歩き方にも様々なものがあります。 歩くことは、単なる機械的な繰り返しの動作以上のものであり、自由の体験であり、緩慢さの練習であり、孤独と空想を味わい、宇宙空間に体を投じることでもあります。 著者のフレデリック・グロが、哲学的な瞑想の連続を読者とともに探索しながら、ギリシア哲学、ドイツ哲学と詩、フランス文学と詩、英文学、現代アメリカ文学等の、著名な文学者、思想家の歩き方について探求します。 ソクラテス、プラトン、ニーチェ、ランボー、ボードレール、ルソー、ソロー、カント、ヘルダーリン、キルケゴール、ワーズワース、プルースト、ネルヴァル、ケルアック、マッカーシーらにとって、歩くことはスポーツではなく、趣味や娯楽でもなく、芸術であり、精神の鍛練、禁欲的な修行でした。 また、ガンジー、キング牧師をはじめ、世界を動かした思想家たちも歩くことがその知恵の源泉でした。 歩くことから生まれた哲学、文学、詩の数々に触れてみましょう。 出版社:山と渓谷社 発売日:2025.2 判型・製本: A5判 ページ数:304
-

『手段からの解放』 國分功一郎
¥968
「楽しむ」とはどういうことか? 『暇と退屈の倫理学』にはじまる哲学的な問いは、『目的への抵抗』を経て、本書に至る。カントによる「快」の議論をヒントに、「嗜好=享受」の概念を検証。 やがて明らかになる、人間の行為を目的と手段に従属させようとする現代社会の病理。 剥奪された「享受の快」を取り戻せ。 「何かのため」ばかりでは、人生を楽しめない──。 見過ごされがちな問いに果敢に挑む、國分哲学の真骨頂。 出版社:新潮社 発売日:2025.1 判型・製本:新書 ページ数:208
-

『目的への抵抗』國分功一郎
¥858
自由は目的に抵抗する。 そこにこそ人間の自由がある。 にもかかわらず我々は「目的」に縛られ、大切なものを見失いつつあるのではないか――。コロナ危機以降の世界に対して覚えた違和感、その正体に哲学者が迫る。 ソクラテスやアガンベン、アーレントらの議論をふまえ、消費と贅沢、自由と目的、行政権力と民主主義の相克などを考察、現代社会における哲学の役割を問う。 名著『暇と退屈の倫理学』をより深化させた革新的論考。 出版社:新潮社 発売日:2023.4 判型・製本:新書 ページ数:208